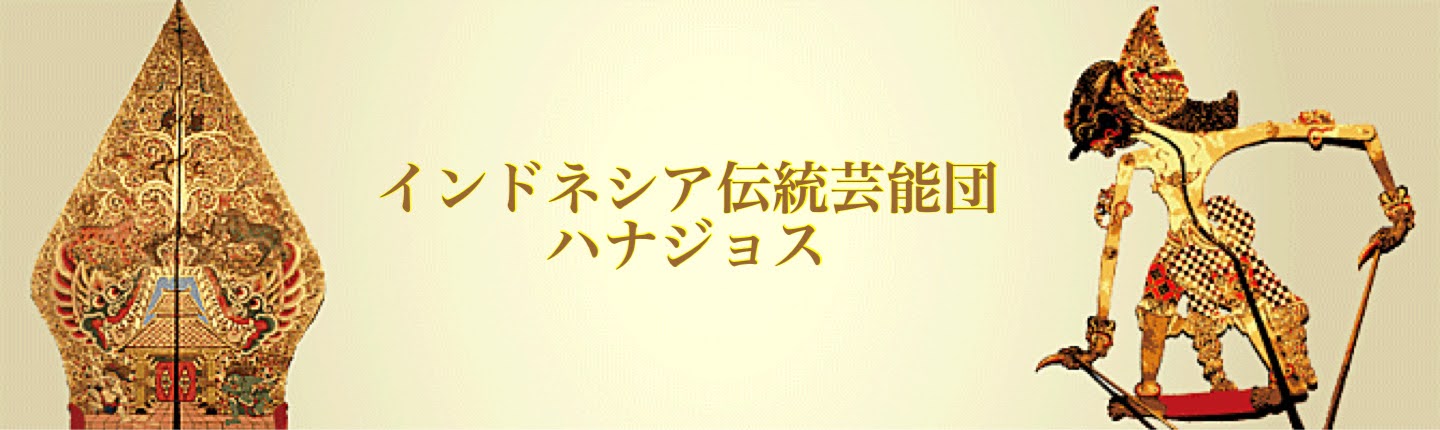ガムラン奏者、佐々木宏実さんの「私のイし(インドネシア推し)」は、インドネシア人の素晴らしい(?)ネーミング・センスです。「技を磨き、隙あらば技を繰り出している」、その「名付けの技」とは?
文・佐々木宏実、写真・佐々木宏実、+62編集部
「目玉焼き」は恐怖のイメージ?!
朝ごはんの定番、目玉焼き。もちろん炎に焼かれる目の玉なんかじゃない。見た目のそれっぽさから、どこかの誰かがそう名付け、いつしか定着したのだろう。私が生まれる時にはもう目玉焼きはあったから、私は目玉焼きにいつ出会ったかを覚えていない。目玉焼きと聞いて驚いたり、怖がったり泣いた覚えもない。卵料理だということを、経験から知っていたから。でも大人になって、炎に焼かれジュージューと蒸気をあげる目玉を思い、しばらく食べられなくなったことはある。

今は目玉焼きも人形焼きも怖くない。回転焼きも。時々浮かびそうになる恐怖のイメージは、その食べ物とは何の関係もないことを知っている。それでも浮かんでしまったら、頭を振ってそれを蹴散らすか、つべこべ言わず食べてしまうに限る。美味しいのだから。
想像力が暴走する、インドネシアの食べ物の名前
インドネシア語(とジャワ語)には、大人になってから出会ったため、音の響きや食べるといった感覚的な経験を重ねそれが言葉と結びつく、という母語の習得プロセスとは違って、まずその言葉の意味を学んでしまうので、意味の力に引っ張られて、時に想像力が暴走し、とんでもないイメージが脳内に広がってしまうことがある。それにインドネシアの名付けのセンスには、なんというか、そう至らしめる技があるようにも思うのだ。
目玉焼きはインドネシア語でトゥロールマタサピ(telur mata sapi)、牛の目。牛の目……ぎゃーーーとなった後、目玉焼きだって目玉焼きだ……となり、想像が膨らみ、しばらく食べられなくなったことは上で書いた通り。続いて、水牛の目。ジャワ語でモトクボ(moto kebo)。これはすりおろしたココナツを使ったもちもちのお菓子で、水牛の目のように丸く、なぜか真っ赤な色をしている。充血……?


テンペボソッ(tempe bosok)は腐ったテンペ。ちなみにテンペと同じ大豆食品である豆腐も、腐った豆と書く。でも腐ってるという意味ではないし、それでも想像してしまうという脳のいたずらも、豆腐には起きない。豆腐が身近すぎて、文字に違和感を抱くことができないのかもしれない。さあ、テンペボソッはどうか。テンペは、菌は違えど納豆と同じ発酵食品。テンペボソッは、発酵がさらに進んだテンペのことだった。美味なり。
とろりとしたバナナを包んだパイのようなお菓子、ピサンモルン(pisang molen)。ピサンがバナナで、モルンはミキサー車のこと。口に広がる美味しさを感じながらも、うなりをあげるミキサー車から何かザラザラしたものがピサンモルンに注がれていく……。サクサク生地やとろとろバナナの中に、あるはずもないそのザラザラを、舌が探す。


ウェダンウォ(wedang uwuh)はゴミ茶。乾燥した木の枝や皮、葉っぱに加えて、グラバトゥ(gula batu)、石の砂糖がセットになっている。全てグラスに入れて熱湯を注げば、透き通った赤い色まで美しい、健康的なハーブティーの出来上がり。確かに見た目は、拾った落ち葉や枯れ木を小さくちぎった、ゴミの詰め合わせのよう。だからってゴミ茶、そうくるか。ならばくず湯だってもしかするとク……、それはない。


その名を知ってしまったその時に、もうきっと食べられないと悟った食べ物が、エステレル(es teler)。テレルは酔うという意味、酔いしれるほど美味しいということなのだろう。しかし最初に聞かされたテレルの意味は、鼻だれ、よだれ、耳だれ。体調が悪い時や酔っ払った時に穴からいろいろ垂レル、それがテレルだというのだ。
本当はメレル(meler)という言葉に、よだれという意味がある。しかしテレルとメレル、言葉の響きが似ているのと、テレル(酔っている)時には、つい口からメレ(垂れ)てしまうことから、ジャワのおじさんはテレルにメレルを連想するらしい。知らんがな。

そう聞いてから視界に入れるエステレルは、実にドロっとして見え、その白くて甘い液体の中では、ショートパスタのような形をした緑やピンクや白濁のジュルジュル物体チェンドル(cendol)が浮いたり沈んだりしている。怖すぎだろテレル。こんな名を付けたのはいったいどこの誰なのか。出てこい名付けの匠よ。どうしてこの名でいけると思ったのか。この名が定着したということは、周りの反応も上々だったのか。
エステレルはエスチャンプル(es campur)やエスブワッ(es buah)と似ている。いっそこの三つが一つになり、名がテレル以外のどちらかになれば、私から怖いものが一つなくなる。しかし、それは身勝手というものだ。うちはうち、よそはよそ、テレルはテレル。
私に烈しい出会いをもたらしておきながら、ジャワのおじさんである夫はエステレルが大好き。嬉々としてズズズと食すその姿を見届けるのが、名付けの匠に敗れし者のさだめなのであろうか。
食べ物以外にも、ゆかいな名付け
名付けの匠が技を繰り出す分野は、食べ物に限らない。
トコバグース(toko bagus)は、バグースな店、つまり素晴らしい店。店主の気合いと自信と商魂が露わになっている。店がその名の通りバグースならそれでよいのだが、どこがバグースなのかわからない、と思えた時こそ楽しくて、こんなにも強気な名を付けたのはなぜか、店主の今の思いは、またこの店のバグースっぷりに自分が気づけていないだけかもしれないという疑い、など想像力フル稼働で楽しめる。結果、通うことに。
トコルマヤン(toko lumayan)、まあまあな店。「品揃えはまあまあや、品質もまあまあや、知らんけど」といったところか。こちらを構えさせない、ほどよい力の抜けように、期待のハードルは下がるので、欲しいものがなくても諦めがつくし、あったら感動できる。「思たよりええ店やんけ」となって、やはり通うことに。
乳歯が抜けて前歯がない時期の子を、「サピオンポン(sapi ompong)、歯抜けの牛〜♪」と好きな節をつけて歌い愛でるお母さんやお父さん、おばあさん。ちなみにサピオンポンは、乳歯ではなく永久歯が抜けてしまったおじいさんのことだったりする。昔のドラマにこんなセリフがあった。林の中でひとしきり闘いが続いた後、主人公が相手に叫ぶ。「このサピオンポンめ!!」
インドネシアの名付けの匠は、今なおどこかで技を磨き、隙あらば技を繰り出していることだろうから、これからもきっと、ゆかいな名付けに出会えるはずだ。
佐々木宏実(ささき・ひろみ)
ガムラン奏者、「インドネシア伝統芸能団ハナジョス」メンバー。大阪在住。Webは下記。